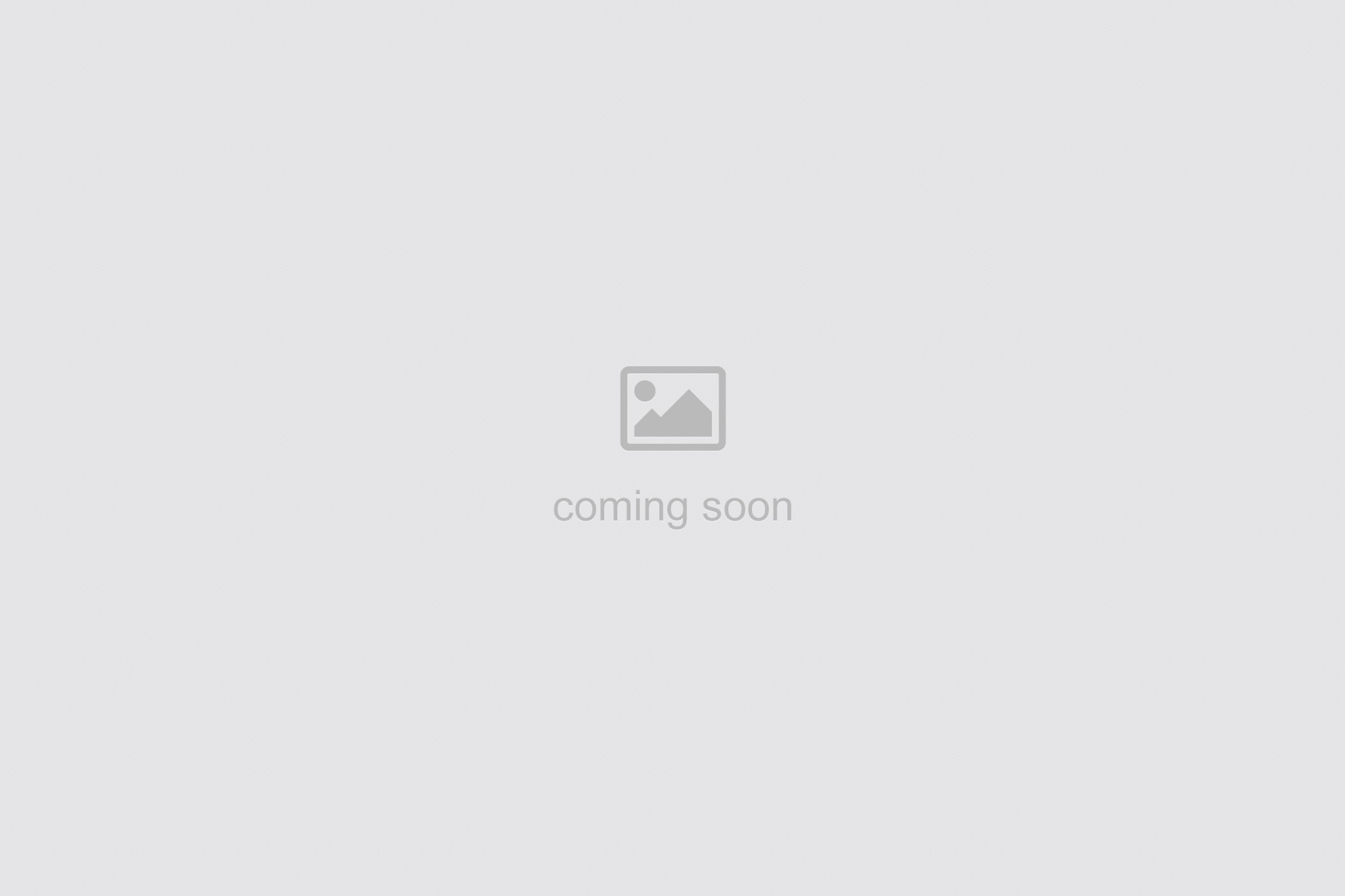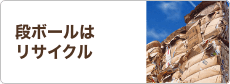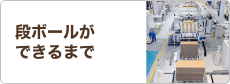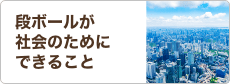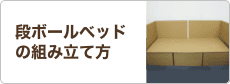もっと詳しく!段ボール箱をつくる(製箱工程)
製箱工程では、「段ボール」に印刷、接合、打抜などを施し、用途に応じた「段ボール箱」に仕上げます。
(1)印刷機:プリンタースロッタ
デザインを施した印版にインキを転移させ、段ボールに印刷を施すとともに、けい線・溝切り加工を行う機械です。
使用するインキの種類によって、フレキソインキを使用するタイプと、速乾性インキを使用するタイプがありますが、現在では、フレキソインキを使用し、アニロックスロールを用いて印版にインキを転移させるフレキソプリンタースロッタが主流となっています。また、安定した膜厚のインキを塗工するためにインキのかきとり機構として2ロール方式とチャンバーブレード方式があります。
使用するインキの種類によって、フレキソインキを使用するタイプと、速乾性インキを使用するタイプがありますが、現在では、フレキソインキを使用し、アニロックスロールを用いて印版にインキを転移させるフレキソプリンタースロッタが主流となっています。また、安定した膜厚のインキを塗工するためにインキのかきとり機構として2ロール方式とチャンバーブレード方式があります。

排出側(シートスタッカ)

給紙側

(2)フレキソフォルダーグルア
0201形(旧呼称:A-1形)の段ボール箱を製造する機械で、印刷、けい線入れ、溝切り、接合、箱成形までを1工程で行います。

(3)打抜機:ダイカッタ
平盤ダイカッタ(プラテンダイカッタ)
平らな抜き型を用いて、上下運動をさせることにより段ボールを打ち抜く方式です。この機会は給紙部、打抜部(プラテン部)、屑取部(ストリッピング部)、切離部、排出部により構成されています。

ロータリーダイカッタ
この機械はわん曲した抜き型を用いて、回転させることにより段ボールを打ち抜く方式です。

(4)ワンタッチグルア
打抜機にて加工した段ボールに、底貼りやサイド貼りを施して特殊形態の段ボール箱を製造する機械です。

(5)ステッチャ
接合部を金属製の平線で留める装置で足踏式と自動式があります。通常フォルダーグルアで生産できない大形ケースや変形ケースの接合に使用します。
(6)結束機

一定枚数の段ボール箱を、ポリエチレン(またはポリプロピレン)の紐を用いて結束する機械で、自動式と半自動の足踏式があります。
(7)印刷インキ
段ボール印刷用インキは油性、速乾性、フレキソの順に発展してきましたが、現在では油性インキはほとんど使用されておらず、速乾性インキも僅かであり、フレキソインキ(水性インキ)が主流となっています。
フレキソインキの成分および色調は下記の通りです。
フレキソインキの成分および色調は下記の通りです。
フレキソインキの成分
- 着色剤
ほとんどの色相で有機顔料が使われています。過去には無機顔料が一般的でしたが、有害な重金属を含んでいるものが多くあり、現在は無害なものだけが使われています。 - ビヒクル
着色剤の分散、印刷適性の付与、塗膜物性の向上および着色剤を被印刷体へ固着させます。
水性インキでは、アルカリ可溶の水溶性樹脂とエマルジョン樹脂が使われ、エマルジョン樹脂は乾燥性・光沢・耐性向上などの機能を有しています。 - 補助剤
印刷時の作業適性や印刷物の耐性を付与するために、ワックスや消泡剤などの補助剤が使われます。

フレキソインキの色調
段ボール印刷用インキは、全国段ボール工業組合連合会、全日本紙器段ボール箱工業組合連合会および印刷インキ工業連合会で標準色18色を設定しています。
(8)接合用接着剤
段ボール箱の接合用接着剤は、一般的にポリ酢酸ビニル、エチレン、フタル酸エステルを主成分としたエマルジョン系接着剤を使用してきましたが、近年、環境問題から化管法(PRTR法)対応品(ノンフタル酸エステル、ノントルエン、ノンキシレン)のエマルジョン系接着剤に変わってきています。
また、接合用接着剤の塗布方法としては、ロール方式とノズル(ガン)方式があります。
また、接合用接着剤の塗布方法としては、ロール方式とノズル(ガン)方式があります。
(9)印版
現在、段ボール印刷にて使用している印版は、大半が液状樹脂もしくは板状樹脂です。従来は鋳造版やゴム版などを使用していましたが、デジタル製版が一般的となり、現在はほとんど残っていません。
樹脂版はインキの転移性に優れており、作業性など使い勝手も非常に良いとされています。
段ボールに直接印刷するための印版は、下記4種類のうち凸版印刷に分類されます。
樹脂版はインキの転移性に優れており、作業性など使い勝手も非常に良いとされています。
段ボールに直接印刷するための印版は、下記4種類のうち凸版印刷に分類されます。


印版(樹脂版)
(10)抜き型
平型(平盤ダイカッタ用抜き型)
打抜機で使用する抜き型は、機械タイプに応じてベニヤにレーザー加工を施し、切り刃とけい線刃を埋め込んだもので、平型とわん曲した丸型に分けられます。各々の仕様は下記の通りです。

抜き型(刃物:刃物とけい線)

ハンマー木型(製品を切り離す抜き型)

ストリッピング木型(屑落丁用の木型)

ストリッピング木型(屑落丁用の木型)
丸型(ロータリーダイカッタ用抜き型)

ロータリ用抜き型(上部)
ストリッピング用木型(下部)
ストリッピング用木型(下部)
NEXT
(段ボールシートをつくる)